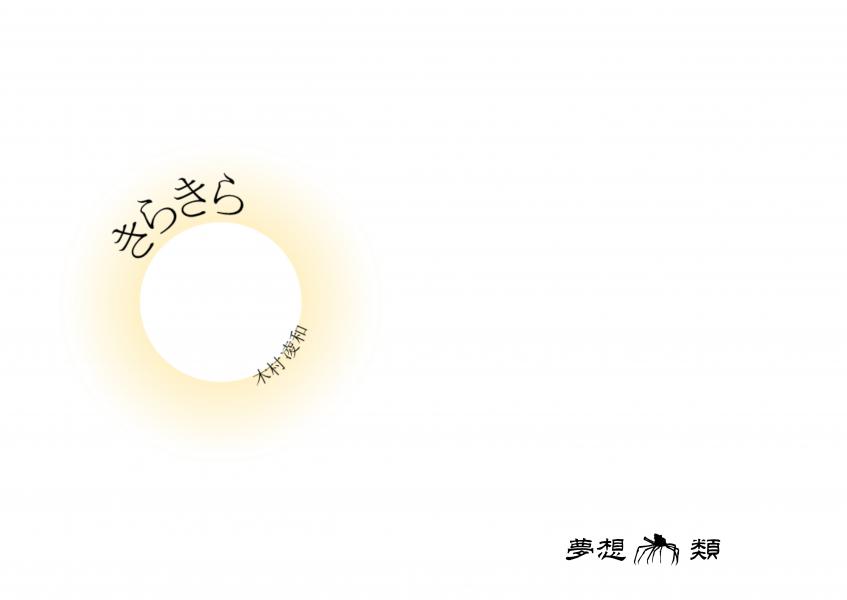|
海が夕陽色にきらきら輝いている。ボクはそれがまぶしくて、細眼になる。堤防に女の人が立っていた。つばの大きな帽子をかぶっているから、ボクを見ているのは分かるけれど顔は見えない。たぶん二十歳くらいで、すごい美人だ。長い髪がとても細くて、きらきらの中に溶けてしまったみたいに、ぽっかり、女の人の輪郭だけがくっきりと影になって、ボクの前にあった。
「ね、どっちにする?」
女の人は両手にカップを持っている。コンビニコーヒーの紙カップ。左右ひとつずつ。全部でふたつ。
「こっちは紅茶で、こっちがコーヒー。紅茶は砂糖入りで、コーヒーはブラックね」
左、右。女の人はカップをちょっと上げて説明する。左が紅茶で、右がコーヒー。
ボクはどっちも好きじゃない。でも、この人がどっちかくれるって言うならどっちか欲しい。どっちにしよう。
「ようく考えてね」
女の人の顔は見えない。でも口は笑っているようだ。きれいなひと。ボクもいつか、こんなふうになれるだろうか。
「あなたは、本を探しているのよね?」
紅茶、と答えそうになったとき、女の人がぱっと言葉を投げつけてきた。
ボクは頷く。
そうだ。ボクにはお気に入りの本がある。それを毎日眼にするためだけに図書委員になるくらいの。ちょっと前までは早く帰って本を読むとかゲームとかしたかったけど、あの本に出会ってからは、あの本のことが頭から離れない。なんてことのない、失楽園の物語だ。主人公は、誰もが憧れるような、月のように、太陽のように、人を惹き付ける人に憧れて、目指す。だが目指せば目指すほど、理想に近づけば近づくほど、自分らしさを失って苦しみ、そのために友人までも失ってしまう。そして最後になってやっと、自らもきらきら輝く存在なのだと、気付くことができるのだ。
あの本は持ち出し禁止だ。分厚い郷土資料とかと同じように。理由は先生も知らなかった。
(「きらきら」より)
|