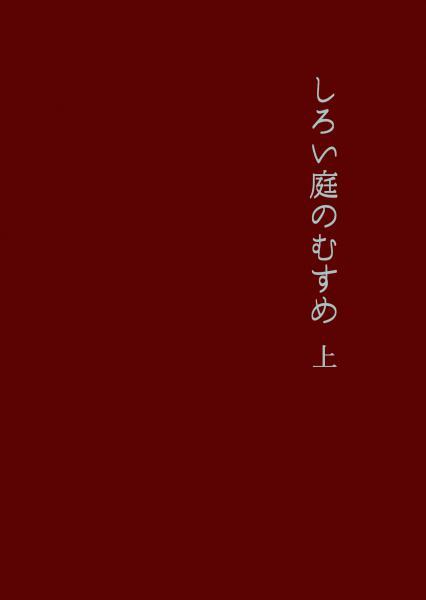|
手をひっかかれながら、イードは猫の頭をていねいに撫でた。
「棲むところが決まらないと、いきものは飼えないな。働いて買え」
「はたらく、って?」
「ここでならおまえも、働いて金を稼げるだろう」
「人間がすることだよ」
「ここではおまえは、人間だよ」
イードは不思議そうな顔でタイスクルを見あげた。
「おまえはここで、猫を飼ったり、鉢で草を育てたり、そういうことをする」
「アルシャは?」
「アルシャだってそうだよ。猫がほしけりゃ猫を飼えばいい、花でも木でも鉢植えにすればいい」
イードは立ちあがり、みみずばれだらけになった手でタイスクルのおおきな手を握った。
「アルシャは猫の代わりにおれを飼ってくれるかな」
「ばか。おまえは畜生じゃない、人間が人間と一緒にいるのは、暮らすというんだ」
「暮らす……? 暮らす」
少年の朱いくちびるが、舌ざわりをたしかめるように何度もその語をつぶやいた。
「タイスも一緒?」
「俺はロイデンスマルトに帰る」
「あの女の人と暮らすの?」
「そうだよ」
「――壊してしまうかもしれないのに?」
それまでの無邪気さをとりはらい、イードは紅い瞳に切実さをゆらめかせた。薄暗い不安にとりつかれている顔。いやなうつくしさだ、とタイスクルは思った。
踏みこんだ部屋に打ち捨てられていた少女の死体。口を血まみれにしたイード。問いただすまでもない惨事。――おのれの欲のかたちを直視したのだ、と、少年は明確な言葉を使わなかったが、打ち明けた。
「そうだよ」
沈鬱にならぬよう、タイスクルは注意して首を振った。
「一度、俺はおまえに言わなかったか。人間は欲を制御できるいきものだって」
「聞いた」
「だから俺はロイデンスマルトに帰る。サリィヤのいる家に帰る。――おまえも、アルシャといていいんだ」
強く手を握りかえして、引っ張る。
そこかしこの飲食店が店を開けはじめて、往来にはいいにおいがただよっていた。腹が減った、と思ったら、少年がおなじことを口に出した。
「ほら、いこう。金が入ったから、なんでも好きなものを食わせてやるよ」
にぎわっているほうへ、二人はむかう。
だれかと街を歩くこと、飯を食いに食堂へいくこと――生活を、これからこの少年がおぼえてゆけるように、タイスクルは願った。
男にあわせて少年が踏み出した一歩は、大きかった。
|