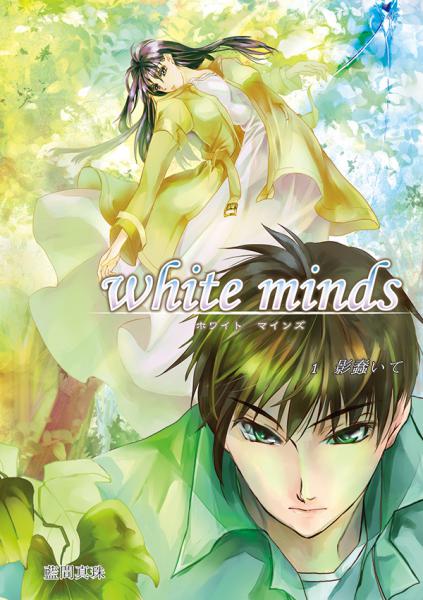|
単独行動に走りがちな仲間がいると、苦労する。かつては自分に向けられていた言葉を、この頃青葉はしみじみ噛み締めていた。
微睡みから抜け出した彼は、すぐに仲間が一人欠けていることに気がついた。異変を感じ取ったのはその後だ。異常な『気』を察知することには慣れていたはずだが、心地よい春の陽気に負けてしまっていた。迂闊だった。
状況を把握した途端、彼は弾かれたように走り出す。ほとんど反射にも近い。慌てたせいで上着を忘れてきたが、寒いと感じるような気温でもなかった。大通りから脇道に入り、さらにその奥の路地裏まで足を踏み入れても、涼しいと思う程度だ。
どんどん道は狭くなっている。まだ午睡中だった仲間たちを置いてきたのは正解だったと、彼は独りごちた。起こすのが面倒だったからというのが理由だが、こんな場所では人数がいても身動きがとれない。彼は短い黒髪を乱雑に掻きむしりつつ、汚れたダンボールを飛び越える。
「まあ、それにしたって、何も言わずにってのはまずかったかもな」
自嘲気味な言葉が漏れたのは、日頃の自分の言動を思い出したからだ。書き置きもなしに一人で動いたのは青葉も同じ。だがそうなった原因は、目指す先にいる仲間にある。
自転車やバイクが目につく狭い路地の向こうには、三つの気があった。そのうちの一つは仲間である梅花のものだ。この異常事態に気づいて一人で探りに行ったのだろう。彼女ならあり得ることだった。
「常習犯だし」
幾つもの文句が浮かんでくるが、それを口にしている時間も惜しい。しかし焦るせいか速度が上がらなかった。障害物も次々と現れるため走りにくい。一度ならず二度も、ペットボトルを盛大に蹴飛ばしてしまった。
それでも路地裏に入ってからは、迷惑そうに脇へ避けていた通行人が見当たらなくなった。もちろん異変を察知したからではないだろう。たまたまだ。一般人は気を感じ取ることができないから、この異常性に気づけるわけがない。
人ならば誰もが持っている気と呼ばれるもの。把握できない普通の人間にとっては存在しないも同然だが、青葉たち『技使い』にとっては違う。何気なく辺りの様子を視界に入れるがごとく、さほど意識しなくともその情報は飛び込んでくる。第六の感覚と呼んでも過言ではない。温度や色で表されることもあり、個々人によって特徴があるのだが、その時々の感情まで反映されてしまう。ある意味厄介なものだった。
|